| 2007年11月24日(土)23:07 瞼で咀嚼。 今日が誕生日で、21歳です。もう昨年から一年……早いなあ。年をとるごとに、時間が経つのがどんどん早くなっていっています。 今年一年の反省。 今年一年は、ひたすら鬱ってましたね!ははは!今年一年というか、今年の二月ごろからか。かなり酷いところまで落ち込んでいたんですが、何度か大小の波があり、今は随分とマシになりました。マシというか、いつまだアップエンドダウンするかわかりませんが、とりあえず小康状態。つい先日に、またかなりダウンしていましたが、持ち直した状態で誕生日を迎えることができてとりあえずよかった! 鬱病じゃなくて、気鬱の類だとは思うんですが、我ながら酷い状況だったなーと思います。いやはや……。随分死にたいな、ぐらいにはなりましたが、死にたくは無いので、とりあえずその心配はしていませんよ!なんだかんだで結構ポジティブっ子ですもの自分! 堕落を求めています。思慮も遠慮も反省も何もかも捨て去ってしまわなければいけない気がする。なぜかはわからないけれど、でも多分、そうしなければ見えない境地がある。たとえば、相手と発話がかぶったときに、止めることをせずにそのまま続けたり(発話を止めることをせず、相手にひかせて)。皮肉や皮肉を言われて、言われるのいやなんだよって意思表示してみたり。でも、やってみると、大体が後悔。しなければよかった…と…。後者の意思表示というのはつい数日前なんですが、確かに何も言わないでその場をすごすよりも随分と気持ちは平常でいられたけれど、皮肉言いたい時だってあるだろうし、言われる原因を使ったいるのはこちらなんだし、言うべきではなかったか。私には無理なのだろうか。発話のかぶりとか、最初の数回は「もう、いい…」と思って遠慮しないようにしていたけれど、やはり、よくない…と思って最近はさらに気をつけてはいる。 でも、私の心が堕落を求めていて、しかしやってみたら否決すべきだと思って、というようなこの一連は、きっと自分のためになる、と信じています。無感動に、無感傷に、箸の持ち方もデタラメで、背も曲げて、足も揃えて歩かないで、そういうことをしてみることが、きっと私には必要なのだろうし、折を見て実践してはいるし、気力の無い時なんかは知らずこうなってしまうけれど、それでも、これらを自分の心が求めたくないとしているのなら、それも大事な心の動きなんだろうな…。楽なことがあって、それでも楽なのはちょっと、と思うのなら、きっとそれには自分の心根の奥の判断が反映されているのだろうと思います。気長に、堕落の論理を探りましょ。堕落は人間にしか出来ないけれど、堕落していない状態であることも、人間の気持ちの成すことだろうから…どちらも知りたいな。あと、自分は楽をすべきなのか、それとももっと厳しくなければいけないのか、そこらへんも見て行こうよ。 自己否定を忘れないように。それをしないようになったら、ただ本当に堕落するばかり。頑張らなくちゃ。頑張らなくちゃ。否定はけして悪いものではないと思うのです。しかし、過剰かと思うときはあるけれど、どこまでなら適当か。とりあえず、否定し続けた先に、否定し切れないものへの肯定があるのだろうと考えるので、多分私の基本は否定系です。自分以外に対してなら、大方ひたすら肯定系ですが!できれば全てを受け入れていければいい、けれど、たまに、自分じゃないものさえどうでもよくなるような…どうでもよくなっても、もしかして、いいのだろうか…うーん…。 基本、自分の心にそむかない限り、「〜しなくちゃいけない」というのはない、ということを、うっかり忘れていたような気もします。鬱思考のせいだろうか…。否定しなくちゃいけないということも、肯定しなくちゃいけないということも、ない、のだろうか。 執着を少しずつ捨てていけている気はします。何もかもから手を離すことはしないけれど、でも、本当にいらないものへの執着は、こうやってほんのり別れられればいいな。でも、たまにものすごく執着してみて、そして煩悩を得ることも必要か。 どちらかというと、シャレやジョークで死にたいとか思えないので、しかし思ったとしても人にそんなこと言うと嫌われかねないので、切羽詰ったときに冗談めかして言うくらいしか出来ず…しかし、そんなもん、人に伝わるわけが無い。辛いなら、もっと辛いというべきか。しかし、それを言って人にどうしてもらおうというのか。自分の中のことなら自分にしかどうにかできないのだし、まず、そういうことを言える相手などいない。でも、誰でもいいから誰かに言いたくなることはあるのだけれども、それはたぶんさびしがりである気がします。哀れまれたら触れてもらえるのだろうか。やっかいだとは思うけれども、人に言わなければ、さびしがりはバレないと思うので、頑張ろう! 私は、自分なら結局大丈夫だと信じています。自分の論理を信頼してるんです。例えば、レポートの締め切りで、あるときまではだらだらしていても、「今からだ」とふと気付いたら、なんだかんだで間に合ったり。多分、私はどんなに堕落して楽になっても、私がそれを好きでないのなら、きっと元に戻るでしょう。でも、堕落しきれない自分が残念です。だって、何よりも悪意は苦手なんです。 一人になると泣き出すし、誰にも知られない状況じゃないと泣けなかったけれど、本当は気付いてほしかったし、誰かのいるところで泣きたかったんです。理解しようとして欲しかった…。どうしようもなく最低な考えだとはわかりつつも、実際そうなのだから、心を否定してはいけない。もう、泣いてばかりでもう嫌だ…。疲れた…。 鬱が創作の役にたつ性質のなら、けして悪いものでもなかったのだけれど、それができないような様相の鬱っぷりだったからなあ…というか鬱時に表そうとすると鬱がスパイラルになりそうだから抑えてたのもあるかもですけど、表現者の端くれとして、押さえてはだめだったよな…でも、この度の鬱の流れは、きっとこれからの糧になるよ。やっぱり体験しないと表現の選択肢ってなかなか広がらないのですもの、多分私は。(想像力がないと言われたらそれまでですが、自分の身に取り入れて、内面化して、そしたら世界の解釈の選択肢がきっと増えるんです。) 自分と他人を区別する必要性がわからない。ただ悲しいだけじゃない。宇宙的意味が主なのですが、別の意味もある。どんな論理もすっとばして、「この人がそうされるのが嫌なら、ああ、うん、嫌だなあ」くらいでいければいい。皮肉の必要がわからない…文芸的言い回しとしてのや、会話上での潤滑油、みたいなのならいいのだけれど、悪意に満ちている皮肉というのは、本当わからない。そんなことしてるより、もっとすべきことしろよ、と思います。悪意は悲しい。 (親を)信じていいんだと、ようやくそう思えたのに、裏切られた、と思ったのが一連の鬱の始まりでしたが、裏切られたも何も、受け入れてくれてるんだと私が思ってただけで、そんな思い上がってた私が悪いんです。一人でなにやってるんだろ。でも、人のことなんてもう信じない、と思ったのに、やっぱり人のこと信じようとしている…。諦め悪いとは思えど、人はそんな悪くないと冷静な部分で思えているのは、喜ばしいことだと思います。 そして、この段落のここまでの文はまだ鬱っている時に書いていたのですが、今思うと、私が人に求めすぎていたのが原因という。人間なんだから、ふるまいをミスすることもあるだろうけれど、基本姿勢が、生かしてくれているというものなら、それでいいという気もします。死ななければ私は良いし、本当に嫌われているのならもう殺されているでしょうし(首を絞められたのは、昔の私のオイタのせいだしな…)、それに、やっぱり家はゆっくり落ち着けます。最近は、声も震えずにちゃんと喋れますし(まだ少し震えが残るけれど、なんかもう、開き直ってきた…というか…)。居心地いいです。 ネガティ時とポジティブ時で、ここまで変わるか…! 何かきっかけがあるわけではなく、突然胸が詰まり泣きたくなることが毎日毎日何回もで、でも人前でそんなことしたら不審がられるだけだから、一人のときはずっと、夜はただでさえよく眠れないので、泣いてました。ずいぶんと落ち着いてはきたものの、何かあったらまた沈みこみそうな……今でも……。見捨てられるのが怖くて、言葉を思い浮かべただけで泣き出すくらいですが、きっともう見捨てられてるようなものだから…あまり個人に固執していると辛いだけだから、受け入れて…身体が生きたがってるんだから、だったらそうしなくちゃ…。 今、絶望していても、来年どうなっているものやら。とりあえず、今年はまれにみる鬱期でした、と。脳のバランスの悪さ、なら鬱病ですが、私は…自分の論理の末にこうなったのだと思いたい…。考えて、考えた末に、現在の状況があり、それは私のそのときの思考の集積であり、そしてこれはきっと自分が自分のために選び取ったことなのだと思いたい。それは精神に偏重してるか。人は心身一元の方がいいのだと思います。運動してないからかな、こんな感情の起伏は。 泣きつける人がいないのは自業自得だものね。というか、そんなことをしなくて済んだのだから、そんな人がなまじいなくてよかったと思います。そんなことしてたら、後で絶対後悔したもの。何も解決しないし、相手は困るし、面倒かけちゃうもの…嫌われかねないもの…。 で、これだけ長く書き連ねてきましたが、結局気分しだいということです。そして、基本的に人生謳歌っぷり。はっはっは。 考えすぎるんですね、多分。無駄にうがって考える傾向にあるのだろうか。でも、自分の考えていることよりも事実はそこまで悪くない、というのも随分とポジティブですね…そして思いっきり逆方向に、考えているよりももっと悪いんだ…と思うこともありで、極端すぎるぜよ。 考えすぎ、というのが、思慮、ならばいいのだけれど、これは単なる固執って感じもするなあ…もっとちゃんと思慮を求めなくては。本当だめだ。自分もそれなりに利するけれど、相手を利するように。全体的視点から見て、自分と自分以外の利益を同じ程度(プラスマイナスどちらでも)にしつつ、やはり自分の内側に適応される論理は違うので!、できるだけ他の人を利することが出来ますように。(誰もがこうしなければいけないという思考ではない!寧ろ自分優先に利する人に対する時の方が、お互い動きやすいこともある…これはまあ関係ないのだけれども。この世にいろんな人がいて、それぞれ、表面に出るものがたとえ似ていたとしても、そこにある論理は、その人がずっと生きてきてここにいるから生まれてくる、それぞれのものである。理解できればいい…理解は無理だろうけれども、できるだけ、その論理に自分の論理を組み合わせられればいいな。つまり、私は目の前にいる具体的な人物のために、自分の論理を目一杯稼動させて、具体的な人のために生きます。) 私がもしも、人の論理を理解しようとしなくなったら、(きっとこれが私の、思慮を失くす堕落の最終地点かもしれない、)もう……どうなるんだろう。それは、随分と精神の死かもしれない。気分的には、死ねばいい、くらいだけれど、そうなったらそうなったで、そこからゆるやかに元に戻っていく気がしてならないので、短慮はしませんように。実行はしないだろうけれど、それでも、多分大丈夫だから。しかし、このような状態から脱却するための死(先程の「死ねばいい」、の死)こそ、鬱で思い患った末の死が消極的死ならば、自分の論理が生きるための、積極的死ではなかろうか。 卒論は、とりあえず「初対面二者間での理由が見当たらない沈黙にどう対処するか」が現在のテーマです。色々知りたいことはあるはずだったのに、いざという時になると何も思い浮かばない、という状況でひねり出したテーマなのですが、これは…うん、実際知りたいところ。小説に反映できそうな内容だ。進めていくうちに焦点の当て所が変わるかもしれないけれど、今はこれで進めて行きたいと思います。 来年は大学四年生で、就職・進学、どうするかを悩んでいます。就職は、公務員がいいかな、と思うのですが…おそらく受ければ通ることが出来るとは思うのですが…それは学問から遠ざかる…。というより、学問から逃げていないか。自分の才能の無さを想う今日この頃でもあるし、よもや探求することから目を背けて楽をしようとしているのではないか。楽はいけない、楽は。…とは言えど、これは、進学を選ぶときにも当てはまるわけで。就職活動とその勉強から逃げて、仕事という重責からも逃げて、それなりに堂々と生きていける院生になろうとしているのではないか。才能も無いのに、逃げる手段に使おうとしているのではないか。とまあ。このように、否定しようとしてみれば、どちらもいとも簡単に否定しうるのですよ。しかし、論理の土台になるべきは心。心の伴わない論理は無意味。さて、心を鑑みると、やっぱり勉強好きだよ…。知る、という行為に近い所にいれるって、すごく幸せなことなんだものな…。 ところで斯様な否定ですが、けして私の本当の論理で否定しているのではなく、生きているうちに得た「選択肢」の組み合わせにより、このような否定が出来上がるのですよ。この、他人に浸食されている感覚が、最近少し不快で…他人が自分の論理の中に存在するのはいいのですが、自分の本当がそれで掻き消されかねないのではないかと、怖いです。まあ、なんだかんだで、きっと、大丈夫、だと思いたい。 そんなこんなで、今日もご飯がおいしいです。明日もおいしくご飯食べれたらいいな!(気持ちの問題で)とりあえず、自分の浮き沈みは、自分に必要だからこうなってるんだろうなーと思うので、好きなように浮いて沈んでいくのがいいのでしょうね。 そして、これから一年も、きっとレディ・ファーストを貫ける…といいな!紳士たるぜよ!堕落の一環で、レディファスしなくなっても、これは多分すぐに思いっきりやめるだろうな…そんなビジョンが見える。 とりあえず、もっと運動しないと…。最近、座っているだけで腕や脚が痺れたりするので、よもやセルライトに血管が圧迫されているのでは、と心配です。大学も三年になると、体育が必修ではなくなったので、ついつい運動不足に。折りを見て動かなくては。体を動かして、今日も元気だご飯がおいしい! 〜しなければならない、というのが世界の普遍の論理としてないのなら、頑張らなくちゃいけない、ということもないのだけれど、私は頑張ることを求めます。頑張る! 今日、集中授業で学校に行っており、母に今から帰るよとメールをしたら、 テレビ買い換えたよとの事。 ……あ、え、早!昨日、どれにしようどれにしようって言ってなかったっけ! 随分前から、テレビの表示部分がだんだん狭くなっていて、端の方の文字とか見えなかったんです。でも、ちょっと欠けるぐらいだったので、まさか本当に買い換えちゃうとは。こんな大きな買い物を。 で、やってきました、フルハイビジョンテレビが。 これが、大きくて、本当に精細に映るんですよ…! 帰ってきてすぐに今までのテレビとお別れ、というのが悲しかったです…トラックに乗せられるさまは、ドナドナを想起させて仕方がありません。今までありがとうございました。 この、このテレビで、早くDVDを見たいな…!! 拍手くださった方、ありがとうございます!!誕生日にこんなに拍手いただけるなんて…何よりもうれしいです。ありがとうございます、頑張ります! |
| 2007年11月22日(木)23:43 論理の炊き合わせ定食 君と僕を心からつなぐ糸 白墨(しらすみ)に溶ける 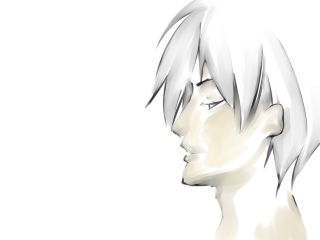 うろでネウロさんを描いてみました  鼻の赤さ練習  鼻が寒いとき、親・人差し・中指で鼻をもにっと押さえてあげると温かいよという平赤漫画  肌の色塗り練習 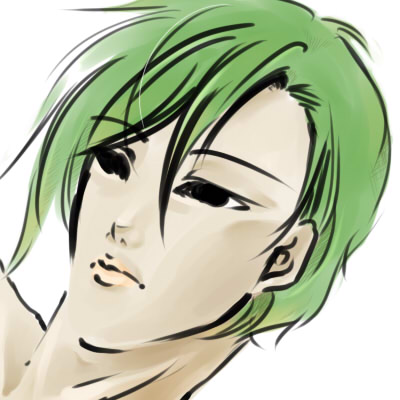 またもや長い間失踪していて…すみませんでした…!! そして、こんな状態だったというのに拍手下された方、ありがとうございました…!活きる活力が湧きます…! 私事なのですが、大学の期末試験期間の最中で、もうしばらく沈没していそうです…今月いっぱいほど。が、24日は、誕生日なので私事の日記を書きにやってきます。 あっという間に11月も末となり、秋を感じ終えるには早すぎる速度で冬が間近に迫ってまいりました。寒い日の続く昨今ですが、ちゃんとお身体暖められてくださいね。 * * しばらくぶりのテレビ感想。 遊戯王GX161・ペアデュエル>先週で、十代がみんなに近づきフラグになってたんじゃないのか…!あれ、お、おかしいな…。あ、あれは万丈目がいたからなのか?万丈目に向かって感情柔らかくなってたって事なのか?という逃避をせずとも、相変わらずのクールっぷりに十代どうしようです。ひさしぶりに楽しい系エピソードかと思ったら…十明日になるのかと思ったら…恋愛フラグを立てるところであえてそれを無視するあたり、GXって感じです…っていうか十明日の人にとってどうだったんだろ…。とりあえず万丈目は可愛かった。とりあえず、タッグデュエルでの非協力っぷりよりも、初心者トメさんに対しても全力で攻撃するあたりの方がアレな感じでどうしよう。いや、どんな相手にも全力で、っていうのはデュエリストとしてあるべきなんだよな…十代もちょっと笑っててくれたし、トメさんが出てくれたしだから、よかった、と言ってもいいか…! それにしても、ここでダークネスを持ち出してくるか。一年目のことがここで出るとは。てっきり、吹雪さんがダークネスに憑依?されていたのって、黒幕の人に勝手にされたんだと思っていたら、そんなうっかり藤原くんのためだったのか!…うん、何が起ころうとも、「GXだから」で済むあたり、GXは恐ろしいです。 160の万丈目がすごく素敵だったんだ!「その時は、オレ達も手を貸すぜ」って!十代、ぜったい救われたと思うんだ…泣きそうな顔してたんだ…!それと、万丈目って「〜だと!?」みたいな驚き系のコメントとか、「アイツは何やってんだ!」みたいな焦れ系コメントとかばかりで、十代負けちゃうんじゃ…みたいな弱気コメントをしやしないんですよね。なんか、きゅんきゅんします。とりあえず、皆が十代の思ってる事わかってくれてよかった! いつか、EDみたいにアニキが笑ってくれればいいな…!また、デュエルを楽しむことを受け入れてくれればいいな…!3年目ラストのあれが、最後のガッチャになりそうで…また、楽しくガッチャって言ってくれればいいな…! 最近のBLEACH>なんか、一護と石田が喋ってるときゅんきゅんします。あの人達、異様に話してないですか(チャドが寡黙なだけでは)。だってさ、「まあまあ落ち着け」って言いたいときに、両肩に手を置いてなだめるものなのか友人は。距離近いよ。そしてこの二人の喋ってる内容は、大体ボケとツッコミとほのぼのな感じで和みます。そしてネルかわいい!かわいい!っていうかこの兄弟&ペットのかわいさはなんだ! Dグレ58「アジア支部」>30分ずっと鬱ってるのかと思ってたから…よかった…アレンが元気になってくれてよかった…!そして、Dグレ劇場は今週の神田君3。ついにアレンさんの魔の手を撃退した神田の可愛さはどうしてくれよう。 * * 今日、「モノノ怪 海坊主」のDVDがアマゾンさんより到着いたしました…!やっぱり装丁素敵だな〜すごく美しいな〜…!薬売りさんの着物が金魚柄に。そして、薬売りさんと幻殃斉が小指で手をつないでいるように見えて我が目を疑いました。疑いましたというか、事実でした。電流走りました。よくよく見てみたら、円形に並んでみんなで小指つなぎしていました。加世ちゃんと薬売りさんが小指つなぎしてるのがとてもかわいい。 11日の、大きなイベント内でのDTBプチオンリー、行けませんでした…。しょんぼり。黒に会いたかったなー…李黒とかニック黒とか11黒とかに会いたかったなー…!冬コミにかけるよ! あと、新聞で見たのですが、ミステリ祭というのがあったらしいのですよ。ミステリ作家とファンの交流や舞台やら。すごく楽しそうでした…!いいな…! あと、新聞広告で見て知ったのですが、百器徒然袋のラジオドラマがあったんですって!まじですか!でも声を聴くのが怖い…どうなってるんだろう…榎木津さん役は、「天国に一番近い男」(テレビドラマ)で甘粕一郎をされてた人らしいんだけど…あれ、どんなお声だったか…。 * * フランソワ・リヴィエール、ガブリエル・ヴィトコップ、訳・梁木靖弘(1989)「グラン=ギニョル――恐怖の劇場」未來社 を5日ごろから図書館から借りて読んでいます。面白いです…!最初は、演劇系の知識が無いのでどういう文脈のうえでこの議論がなされているのか飲み込めていなかったので恐る恐るだったんですが、今はもううきうきしながら読んでいます。 しかし、荒木俊馬(1970,1974)「宇宙物理学」恒星社厚生閣 の方も早く読み終わらなきゃ。一学期から読みはじめたんですが、最近借りていません。というか、ページばらばらに読んでいるので、どのくらい読み終えているのやら…もしかしてもう全部読んでるのか…。 * * 遊戯王GX、ついに24・25・26話を見ました。万丈目がノース校に行き、代表戦をして、本校に戻ってくる、この一連の話。今まで、万丈目が辛いのを見たくなくて、でも絶対大好きになる話だろう予感はあって、と板ばさみだったんですが、ニコニコで見つけて…ついついフラフラっと…。 まあ、なんですか。新しい宗教の誕生する瞬間を垣間見ました。なんだあれは。予想以上でした。すごすぎた。 大量の野太い野郎どもの声援がこんなにも似合う男キャラはいない。そしてノース校の人たちは何で皆あんなに強面なのか。翔、あれはもはや「すごい人気」とかそういうレベルじゃないから。 で、うわさのトイレのシーン、25話だったんですね。このシーン、涙ぐみました。なんだかもう、やるせない。 で、26話。十代が万丈目兄弟に向かって言ってくれたところから最後まで、ほろほろ泣いてました。もう…もう…!!!だって、もう……!!十代が、万丈目のことわかってくれて、いつか本気のお前と勝負したいなって言ってくれて、万丈目がもっとデュエルを楽しんでくれればいいって思って、あんたら兄弟とも戦っていたんだって言ってくれて。万丈目が、帰ってくれって言ってくれて。ノース校生だけでなく、本校の生徒も万丈目のことを応援してくれて。もうこの頃から学園統一アイドルの未来が見えていますね。ノース生たちはみんな泣いて、万丈目が大好きで。ノース校生達はやっぱり最後の最後までサンダーが大好きで。お別れシーンは、お笑いムードで、それがこれからこの子は幸せになるんだよって言っているようで、よけいに涙腺に来て。万丈目は晴れてレッド寮に入って。これから、幸せになるんだから。ああ、ああ、もう、万丈目が、ようやく人にわかってもらえて、本当に誰かがそばにいてくれて、そうなっていくんだもの。そして、十代が、あんなにも面と向かって強く、万丈目のことを語ってくれるんだもの。泣くよ。みんな泣くよ。 本人認めるか認めないかわかりませんが、絶対、十代に出会って、レッド寮に入って、よかったです。ようやく、本当に自分の言葉で喋って、自分のままでいられて、そんな場所に出会えて。これから、いっぱいいっぱい幸せになるんだから。まあ、二年目で白丈目になったり、三年目で異世界に行ったりゾンビになったり光の粒子となったりするけれど、まあ…基本が幸せだったらいいと思います!よ! 私がGX見始めたときにはもうブラックサンダーになっていて、なのでなぜOPで万丈目が青い制服を着ているのかわからなかったんですよ。ようやくオベブルの制服を着て動いているサンダーを拝めました。こうやって青から黒になったんだ…万丈目、本当格好いい…!! そして、第一期OPでは万丈目は敵役の一人扱いで尺が短く、三沢くんはかなり目立つ扱いで堂々としていたのに…期が進むにつれ、万丈目はどんどん目立ってもはやメインヒロインだし(私の眼にはそう見えるさ!)、三沢は… … …うん、OPとまで贅沢言わないので、はやく画面に戻ってきてほしいです。 それにしても、本当ノース生達はサンダーのことが好きすぎてどうしよう! まあ、あんなゴツイ野郎ばかりのところに、突然鮮やかで細くて白い美人さんが来ちゃったんだもんな、宗教の一つや二つは軽いね! 万丈目さん、絶対面倒見のいい人なんだよ。なんだかんだで、自分のそばの人のことを大切にしてるんだよ。そして、人を惹きつける何かがある。万丈目本来のそういうものが、隠さずに出していけるから、これからこの人はこんなにも、寮の色とか関係なくす勢いで、学園のアイドルになるんだ…。 そして、ここから35話につながるわけですが。(ノース校絡みで言うなら、二年目の死神のカードの回も要チェック!)本放送時、この回にはもう見始めてたんですよね。そして、攻撃力0デッキという無茶っぷりなデッキを組んで戦って、そして勝った万丈目さんに惚れた気がします。「悪霊が襲ってきたら、お前を守らなきゃ」で十万にきゅんとした気もします。なんだかんだで捨てられていたカードをみんな拾って自分の部屋に持って帰る万丈目さんの優しさにニコニコニコした気もします。 たしか、18・19話の「VS遊戯デッキ」で神楽坂を見た覚えもあり(主人公の偽者ができてる、くらいの認識だった気がする…もしかして、これ初めて見たGX??)、29話「VSダークネス」で真紅眼の黒竜が出てきてびっくりした覚えもあり、32・33話「VSカミューラ」でエジプト関連ではないけれど闇のゲームをしていた覚えもあり(万丈目にベッドに戻される十代と、万丈目に「うるさい!」と怒られて「はい」となる十代と、人形から戻ったクロノス先生に腰に抱きつかれている万丈目を見た覚えもありますよ!テンション高!)、34話「湯けむり旅情」で万丈目がいきなり足を組んで半裸をさらして、そしてカイバーマンが出てきてから、恒常的に見ているような気がします。でも、41・42話を見た覚えが…それとVS影丸会長は、見たような見てないような…。そしてあっという間に二年目です。 見始めた頃は、てっきり随分前から始まっていたのだと思っていたのですが、今考えてみると、結構最初の方から見ていたんですね。 まあ、あれです、万丈目が好きということです。たぶんGXに本格的にはまったのは35話の万丈目や名探偵万丈目サンダーやいろんなサンダーのせいだと思うんです。そして、いつかの十代の強い思い出は、デッキ破壊デッキ(デッキのカード枚数を0にする)を使ってくる相手に、グローモスでデッキ破壊返しをする図です。正直ちょっと恐かったよ! そしてやっぱり、このコールは見ていると一緒に叫びたくなります。 一、十、百、千、万丈目サンダー!!! |
| 2007年11月06日(火)17:05 なんだかネウロまみれになっています 皆様、拍手ありがとうございます…!11月に入って随分とたってしまって申し訳なく思いつつも、やっぱりみんな平赤好きなんですね…!と嬉しいです(嬉)! うちの平赤は相変わらずな感じですが、もういっそこのままほのぼのしてればいいと思います。ぬくぬくしてろ〜もう! 二回前の日記から引き続き、メルカトル鮎さんでお送りします。 私の好きな探偵のうち、ドSが二人になった記念です。(メルは別にSではないけれど、どう否定すればいいのかわからない…否定できない…) ネウロさんは…きゅんっきゅんだ! そんなわけで、アニメネウロ第五話感想! とりあえず箇条書き。 見下されたい…!天井から、思いっきりネウロさんに見下されたい…!自分の中のMっ気が萌芽する…! 社長…格好いい…!こ、こんな人が亡くなるとか…ありえんよ…! コンビニに近いとか、ヤコちゃんのためやん…!「我輩と貴様と謎だけの空間」とか、何その素敵空間!我輩と謎だけの、じゃなくて、ヤコちゃん含んじゃってるんだぜ! ヤコちゃんもヤコちゃんで、第一話から、ネウロが無事だとわかる度に「ネウロ…」と優しげに言うものだから、ああもうネウロ大事に思われてる! きっと、このメロンはスパッといくんだろうなーとわくわくしていたんですが、いやはやもう、期待以上の見事な切れっぷり!!爽快ですね!! ネウロさんの汗とか、「うわ〜嘘だ〜大嘘だ〜!」ときゅんっきゅんします。ありえんぜよ! まばたきで銃弾挟んじゃった、のシーンを見てまず、「ネウロさん睫長ッ!」です。睫長くないと、あんな銃弾挟みとかできない!(長ければ出来るのか) 「な、奴隷一号?」「なにそれ〜!」って…どんだけ可愛いのかなこのふたり…!仲の良さは、奴隷と主人だとかそういう範疇じゃないよ…! で、最後の最後の 「やなのか?」 って あれなんですか!!正直脳髄も吹っ飛びましたよ!え、ええ、えええ〜…原作ではどうなってるものやら楽しみです。文字だけだったら、もっと格好いい感じの想像になっていたのかもしれなく、あー声は凄い。…うん。な、なんだ、くそ、可愛すぎるだろ…あれは…! アニメ第一話でいきなりネウロさんが素肌晒してものすっごいびびったのですが、あれ…もしかして、ネウロさんって、スーツの下はアスコットタイとベストだけ!?え、なにその破廉恥!第一話の際、「シャツは!?シャツは早脱ぎ!?」と驚愕していたのですが、まさかこんなまっ直線に素肌ベストだなんて…! ネウロさんが人波にいると、あたまいっこ出てて、思いっきり目立つんですよね!なんだか、あの異様な背の高さに胸がときめきました。そして指も長い!黒手袋だ! 以前、第二巻まで発売されていた頃、書店で見かけてものすごく気になって購入しようかどうしようか迷ったのですが(だって魔人で探偵で脳を噛んじゃうネウロさんなんだぜ!)、インスピレーション買いに躊躇したのが敗因でした。中身を見てなかったあの頃からきゅんきゅんしてたんですが、もう…買っちゃおうよ! 髪結びネウロさんが気になって仕方ないです。公式で髪結んじゃったんですってね。なんだそれ、きゅんきゅんじゃないか! ところで、うろ覚えでネウロさん描いた後にちゃんと色々見直してみたら、髪の三角は毛先の全部についてるわけじゃなかったり、黒い前髪は真ん中にも一本垂れていたりと、いろいろな間違いが発見。やっぱりうろって怖いですね! 先月29日に、DTBDVD一巻みたよ!サントラ聴いたあとに見ると、あ・これはあの曲!とわかり、きゅんきゅんが倍増です。 設定資料集は、舐めるように見まくりました。背景資料とか…すごすぎる…。千晶さんのあれは、そうか、放射光に誘われて、の解釈もあるのか…。 ジャンプスクエア買ったよ!かずはじめ先生のLuck Stealerを主な目的に買ったんですが、いやー漫画いっぱいでしたね!かず先生は、相変わらず世知辛い中にも希望を持てる話で…花凛ちゃん可愛いよ…! 遊戯王GX>斎王さまが!斎王さまが!!再☆登☆場…!そして覇王十代さんは言うことキッツイ。 |
2007年10月31日(水)16:43 楽しいハロウィンのために。(平赤)     (調理中)  ちょん。 昨年のハロウィンは、平山が幸せっぽくなっていたので。懲りずに今年も幸せっぽくしてみました。去年よりも…さらに甘くなっている気がします! 去年はシュークリームだったので、今年はパンプキンケーキで。平山ならきっとお菓子作るのうまい。分量・手順共に正確に。 この後、南郷さんや安岡さんや鷲巣様&白服達のところなどなどに、おすそ分けに行ってきます。家に帰ってきてから、残してあったふた切れを、また紅茶と一緒に食べればいいです。 今年はこれで、お粗末さまでした。 |
| 2007年10月31日(水)01:26 虚言症(京榎/京極) 途中までと概観 「虚言症」 誰とでもすれ違う。すれ違うのは、誰でもあるものだ。 学校の教室、学校の廊下、学校の食堂、学校から寮までの道、寮の食堂、寮の廊下。これだけ羅列してみても、顔見知りであるものならば声でも交わして別れるが、すれ違うのは、自分にとって誰でもないものだ。 そこに個人は無い。礼儀としての会釈、道の譲り合い、そのようなものは、社会性のある物体として見ているからに過ぎない。 真実自分は疎外されていると感じられ、真実自分は溶け込んでいると感じられ、真実自分は確固であり、真実自分は漂っている。この、世界に。 自分はいつでも水銀灯の下を歩く。片側に行列する、水銀灯群の下を照らされながら歩く。 暗く明るい。奇妙な配色。 白黒の風景。 埃が舞う空気は、息苦しくはなく、澱みと閉塞感をもたらす。 それさえ、いっそ、どうでもいい、と思いそうになる。思ってもいい。 けして斯様に生きていることが嫌いなのではない。ただ、奇妙なのだ。 配色が。 目の前の景色はいつでも、明るく、暗い。 正直、人の顔も見えない。 顔は見えないが、造形は見え、表情は見え、ついでに声も聞こえる。誰もの造形も表情も声も識れる。なのでこのように毎日社会生活も営める。 しかし、人の顔が見えない。 顔見知りでさえ、誰でもあり、もはや誰でもないものだ。 造形・表情・声はある。しかし、それしかない。というのは、顔は無いというのと同義。 人間は、人間の顔を良く判別すると言う。 自分は、人々の顔が見えない。 すれ違う人に到っては、顔が見えないどころか、まず、何も見ようとはしていないが。礼儀、自然さ、そのために必要なものだけ見えている。 斯様にすれ違う。 するり。 「君、本に埋まってるのかい?」 その声。声だけだった。よりにもよって声だけだった。、には、 表情が含まれていた。色も含まれていた。 鼈甲、紅(べに)、群青、翡翠、灰色、肌色、黒色、白色、色が極彩色に含まれている。 自分にはわかった。これ、この声には、色があるのだと。 耳だけがそれの方を向いていた。両耳だけ向いていた。しばらく耳だけ向けていた。しかし、両の眼球が硬直したまま動かないまま、瞳孔が妙に収縮していくのをようやく意識し、ようやく顔ごとそちらに向けた。 ゆっくりと見えてくるその、人間、の姿。俯き気味だったため、下から見えてくる。制服の靴、ズボン、上着の裾、白い指、少し広げられた両腕、肩、胸、喉元、白い首、白い顎、薄桃の唇、ほほえんでいる、通った鼻筋、長い下睫毛、奇妙な目、ぼやけているのか焦点、瞳孔、白い額、鳶色の柔らかい髪、楽しげな眼。 それは、人間で、男だった。年は、上か。 眼球は硬直したままだ。喉も硬直したままで、しかしそれはいけない。震わせ、 「どういう」 「どういうじゃアないさ。君の向こうに大量の本だ。何だソレは、古い。古すぎる!ぼろぼろだ!あと、その部屋は暗すぎる!もっと明かりを点けたまえ!眼が見えなくなるよ。」 「どういう意味で」 「意味も何もないよ。本で窒息死するつもりなのか?それは面白い、やるんだったら僕も試してみたいな!何だ、それは……仏蘭西語か?そんなのにまで埋まる気なのか。面白い男だなあ」 「何」 「何、何だって?楽しそうだなあっていうことだよ。全面、本で埋まってるじゃないか。地震が起きたらパアだな、パア。オダブツだ。とりあえず窓くらい作りたまえ。開け給え。のこぎりなら倉庫にあったから、そうしなさい。あと、本当にランプは要るよ。燃えてしまうかもって思ってるのかい?」 「」 「大丈夫、大丈夫。何のための硝子の覆いなんだか。安心して明るくしたまえ。それに、外に出て読むと手っ取り早いよ。お日さまだ!」 「本が日焼けするんですよ」 「そりゃあ生きてりゃ日焼けぐらいするだろうさ。でもそれが何なんだい。たまには外に散歩に連れてってやると、きっと喜ぶよ!」 「散歩」 「そう、散歩」 一度、ダン、と右足を踏み鳴らす。濃い影が地面から浮いて、勢い良く着地する。 「こんな風にね。」 そういえば、今日は晴れていたのだ。 「まあ……散歩ね……」 「そうだ。動け動け!いっぱい動け!」 「善処はしますよ」 「そうダそうダ! ン、君は本当に本ばかりだな!すごいな、すごいな!面白い男だなあ」 奇矯というべきか、しごく理性と言うべきか。何の違和感もなくなって来てしまっている、この会話に。 それにしても、あんた、誰だ。 記憶にあるような。しかし、ごく其れは薄く、 「そういえば、おなか空いたな。君がそんなもの視せるからだゾ。」 食堂? そういえば前、食堂、遠く、人の輪の中に居た誰かを見た気が、 僕が何を見せたと。 「今日は何だろうな。じゃあね」 片手、ひらひら。 眼をほんの僅か見開こうとする合間に、あの人間は、僕に笑いかけ、にっこりほほえみかけ、あまつさえ手まで振って、横を通っていった。 けして、すれ違う、のではなく。通っていった。 彼の通った後、残像さえ見えた。色鮮やかな陽炎。 校舎の角に、彼はもう着いた。そしてそこで、ひとつくるり。左足を軸に右回りをし、 笑った。あまつさえ、首をくいっと少しだけ傾(かし)げて。 そして影一つ残す。それも、形を保ったままに、動いて見えなくなった。 ただ意識のすべてを持って行かれた様な気がした。 * * 「なんだよ、中禅寺。お前、榎木津先輩のこと知らねえの?」 「榎木津?」 「有名だよ。一つ上の先輩で、文武両道眉目秀麗、出る案は意外なところから吹く神風のようで、する事は的を射抜く銃撃のよう。帝王、だと。」 「ふうん。」 「どうしたんだよ。」 「いや、何。それはすごいな、と。どんな人なんだい。」 「色が薄いって聞いた気がするな。や、俺も直接見たこと無えから」 「ふうん。」 この一連の話の始まりは、「相変わらずあの人はすごいな」と誰かを絶賛する言葉に、誰のことだいと尋ねたのが始まりだった。今は、どんな何よりも、 名前、名前、名前、 が欲しかった。誰の名前でもいい、話題に上る人間の名前なら有効だ。どうやら、 いいことを、聞けたらしい。 恐らく、これだ。 あれから、たまにすれ違った。いや、横を通り合った。 大体、彼が、廊下の随分と離れた位置から声を掛けてくる。その声に、ひくりと首を持ち上げ、その笑顔を見ながら、無表情に近づき、少し喋って、横を通り合う。 喋る内容は、概ね突拍子も無いこと。彼からの話題は大体そんなものだ。 奇矯、奇妙、不可思議、しかし狂人ではなく、聡明。恐らく、自分が知るよりも、透明な聡明さ。 信頼、といっても差し支えは無いだろう。彼の喋る内容は、唐突かつ何段も飛び石を重ねているが、そこには確実な理性と、彼の真実があるのだと、そう思える。 その理性。それを、こうも信じられる。 狂人のようであり、おそらく限りなく透徹。 何度も交わされた会話の内容は、飛び飛びだ。しかし、意図は伝わってくる。そして、相互伝達可能な組み立てで、発話をする。 そこにある論理。 何度も何度も交わしているうち、自分の頭の中に、彼の論理が芽生えていった。 情報を採取、今までの論理との適合性を判断、受容か拒否、拒否ならば新しい仮説を、需要ならば次の仮説検証へ、たまに構築されてきた論理を確かめる、 そのようにして、彼の論理、彼の論理の基になっているもの、彼の状況、その理(ことわり)。それらが、見えてきた。 しかしどうにも。名前など、聞ける筈が無い。それは果てしなく無粋な上に、きっと彼は残念がるか、寂しがるか、くだらながるか、切って捨てるだろう。つまらない、と思うのかも。 名前を訊く事を、か、自分を、かはわからない。 それに、そのような考えをする前から、なぜか彼に其れを訊くのはためらわれた。知らないまま、名前など知らないまま、このような個人で居て欲しい、と思ったのかもしれない。真相は判らない。 しかし、ある時、彼が僕の後ろに僕が僕の名前を見ている光景を見て、「ああ、君、中禅寺っていうのか!」となんの憂いもなく言ってのけたものだから。そしてそのまま嬉しそうに笑いながら去っていったものだから。 だったら、無性に知りたくなってきた。堰が切れたような心持だった。 なので。彼なら、多分噂や話題に事欠かないだろうな、とひしひしと感じていた。彼と話していた時の周囲の視線は、いつも厚く、熱かった。 だから、誰かの噂があれば、相手が会話中だろうが訊く事にした。冷静に、物腰柔らかく、しかし焦(じ)れて。 話を聞いていくうちに、ああ、こんなものは彼ではない、と思うことばかりだった。 何度焦れ、何度見切ったか。 しかし、何度それらを重ねても、落胆や失望など一片も挟まれず、ただ次の機会を探していた、 今日、この教室で、隣の生徒が発した言葉。それにも、やはり好機を見た。人の口で伝わる情報の中にも、きっとどうしても彼の姿はにじんでいる筈だろう、誰の口を介そうと、自分なら選(よ)り分けて得られる。そして、ようやく、知った。 知った。 榎木津。 知った。 毎回の新しい好機の度、持ち越されてきた感情が、今回胸のうちにようやく発露する。 じんわりと、高揚感。 「やあ、中禅寺!」 「どうも、榎木津先輩」 そして、次に逢った時、ずっと以前からそうであったように、名前を呼び合い、話し、通り合った。 * * 何度も話していると、そういえば、段々と……発話と発話の繋がりが、より見え難くなっている気がする。しかし、見える。 「あんた、最近喋るのに手ぇ抜いてませんか」 「そうかなあ。多分、中禅寺だからじゃないか?お前ならわかってくれるもの。わかってくれてるじゃないか。」 「なるほど、ね。」 僕は、あんたを信頼しているのと同じように、あんたに信頼されているらしい。 あんたの論理を、その言葉と言葉の間を、僕なら繋ぎ止められると。そういうことを、この人は謂っている。 でも、いいんですか? 僕に悪意があるんなら、いつでも、どうとでも、あんたの論理なんて滅茶滅茶にしてやれるのに? 『わかってくれてるじゃないか。』 あんたは、何でそう確信なんて持てる。 * * 本当か? あんなに――大きな、眼なのに。 「見えないんですか?」 顔を寄せて。 否。見ようとしていないのか。 「先輩。見えていますか?」 僕が。 * * 「ああ、お前の周りはそおいうのばっかりだな!」 「まあ、そうですね。」 様々な宗教、それについての知識、そして理解、そして実践の際の感情、論理。それらを知りたく、また知らなければならない。そういうものなのだ。 そして、宗教に、焦がれはしないが、実践への欲求はある。しかし、どんな宗教にも近ければならないが、どんな宗教からも離れていなければならない。どんなものにも近くなるため。だから、どんな神も信じるわけにはいかなく、また、どんな神も信じられそうにもない。自分は。 「宗教は、厄介なんですよ、知るためには。信じきってしまったら、知ることから遠くなるが、信じきってしまわなければ、知ることに近づけない。」 「ふうん」 「まあ、知ろうとはしますが、しかし。どうすればいいものやら、未だ僕は、掴めて」 「じゃあ、中禅寺。 僕がお前の神になるよ。」 「――」 「僕を信じろ。僕を崇めて讃えて、とは謂わないがね、信じろよ。 僕がお前の宗教になってやる。 僕を信じていればいい。」 「――」 「どうだ。」 「――あんた」 「なんだ」 「――感慨深いですよ。」 嗚呼、宗教を得たり。 * * 「僕を呪え、中禅寺」 * * ずっと以前から、書こう書こうと思っていた京榎「虚言症」。ふと、書きたくなりまして。 もっと、開始直後から榎木津さんとすれ違うはずだったのに、妙に冒頭が長くなってしまいました。 「僕がお前の宗教(お前だけの神)になってやる!」も、高校の頃から書きたい書きたい思っていたところです。中禅寺さんの反応については考えていなかったので、今考えましたが。何で中禅寺さんの神になってやる、と言ったのかも、今。今考えたつながりで、「嗚呼、宗教を得たり。」の一文は、別のものでもいい。 「僕が見えていますか?」の一連は、20041025日記に記述したままで。 榎木津先輩の名前探索の章や、君だからこうなんだよの章は、今考えたもの。 * * 呪え、という言葉はとても穏やかに発されて、透明な両の瞳も穏やかで、ああ、真実だ。 いいの。 僕をあんたに刻み込んで、いいの。 あんたは一度も嘘なんてついた事が無いね。僕は、真実かどうかだなんて事を考えてしまう程にしか、あんたを信じていなかったのだろうか。 あんたの言葉が嘘なら、あれも、これも、出会ってから今までこの瞬間までのどの言葉も全て嘘だったろう。あんたの言葉が嘘なら、僕の言葉も嘘で、あんたの世界も嘘で、僕の世界も嘘だ。しかしあんたに嘘などない。 虚言症というものに毒されていたのは僕だったのだね。 いいんだね。 僕をあんたに刻み込んで、いいんだね。 |
| 2007年 | 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 |